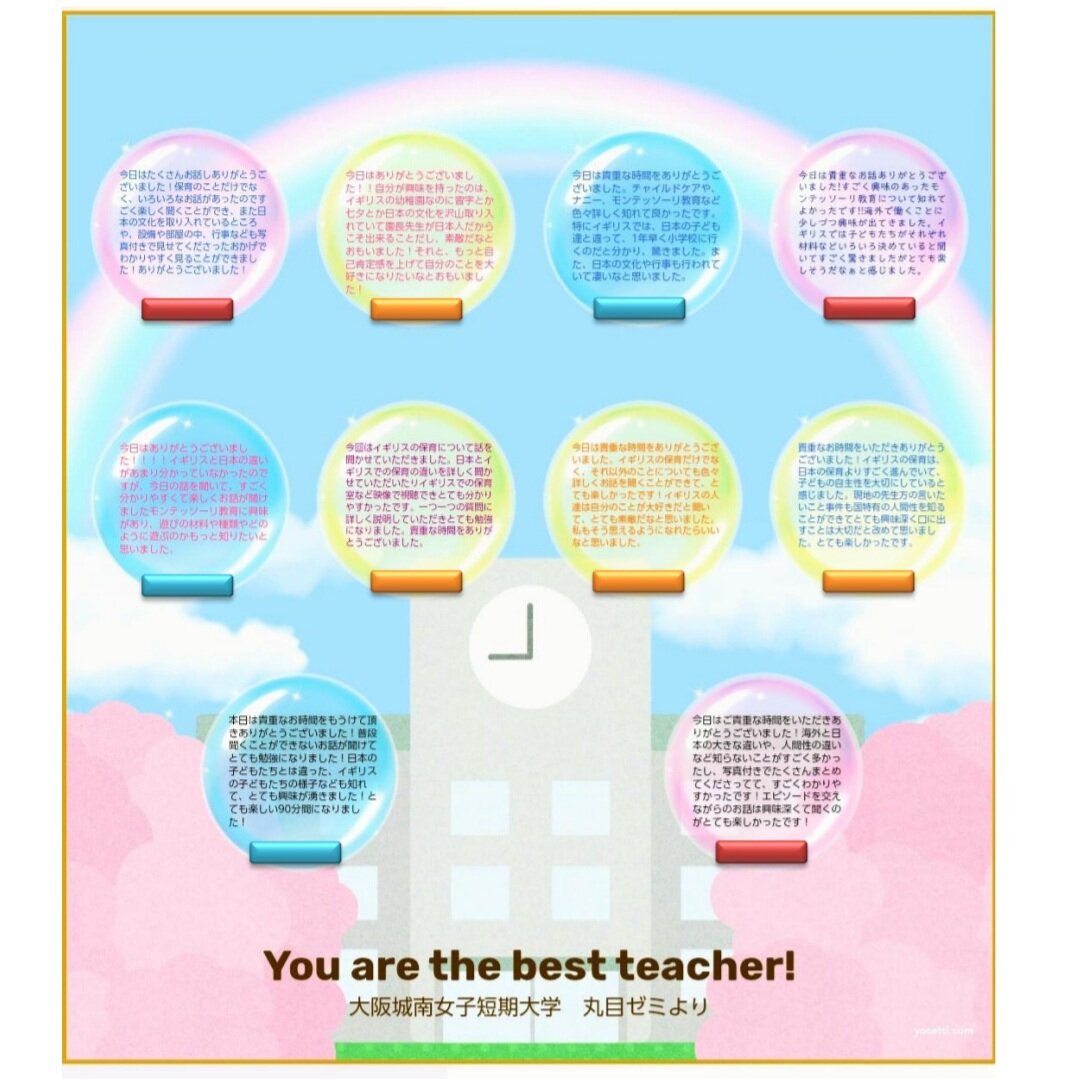シリーズ【イギリスの幼児教育】 第9回:乳幼児期に形成される親子の絆の大切さを提唱した ジョン・ボウルビィ (その2)
前回は、イギリス人精神科医のジョン・ボウルビィ(John Bowlby, 1907–1990)の、生い立ちや初期の頃の経歴を紹介しました。今回は、ボウルビィが定義した愛着が築かれていく段階と、乳幼児期に愛着がその後の人生に及ぼす影響について紹介します。
子どもが健やかに育つためには、親の愛情やケアが欠かせません。
ボウルビィは、人格形成の基盤が築かれる乳幼児期の親子の絆に着目し、数々の研究を基に1969年「アタッチメントセオリー(愛着理念)」を発表しました。
その中で、ボウルビィは子どもの社会性や情緒面の発達には、0歳から3歳までの乳幼児期に、最も身近な養育者(通常は母親)との間に築かれるアタッチメントと呼ばれる愛着が重要な役割を果たすと述べています。
また、特別な人への愛着は、私たちが生まれながらに持っている生存能力で、赤ちゃんが泣いたり、微笑んだり、近寄ってくる愛着行動に、親が確実に応えることで、親子間に相互に育まれていくと言います。
ボウルビィが定義する子どもが愛着関係を構築していく過程は、表1にある4段階です。
これを見ると、愛着は生後3年間*の親との初期関係によって、形成されることが分かります。
では、反対にこの大事な段階に、しっかりとした愛着を築けないと、どうなるのでしょう?
その場合、子どもはその後の人生を豊かにするための土台が欠如し、自己肯定感の低さなどの情緒面や人と信頼関係を築けない、人とうまく関われないなどの対人関係の問題を生涯抱え、取り返しのつかないことになると、ボウルビィは警告しています。
ボウルビィの理念が、日本で昔から言い伝えられている「三つ子の魂百まで」と並行して語られるのは、こういった背景から来ているのでしょう。
*ボウルビィは、0~3か月までをcritical period、5歳までをsensitive periodと定義しています。
次回は、ボウルビィの「アタッチメントセオリー」が、保育や子育てにどのように反映されているのかを紹介します。
おすすめ情報
関連の話題
海外保育のトピックを検索